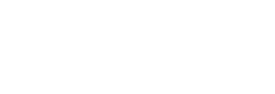序章:一杯のお茶に宿る、二百年の物語
華泰茶荘は、単なる茶葉を商う店ではありません。それは二百年の時を超え、台湾茶の真髄と文化を護り、そして伝え続けてきた一族の物語そのものです。
福建省安渓の地から台湾へと渡り、この地に茶業の根を張った先祖の志。その情熱は五代にわたって脈々と受け継がれ、一杯のお茶の中に深く息づいています。
この物語は、皆様を時間と国境を越える旅へと誘います。伝統が革新と出会い、文化が海を越えて新たな花を咲かせる、華泰茶荘の軌跡をどうぞご覧ください。
源流:安渓から台湾へ、茶業の礎を築く
全ての物語には、始まりの場所があります。
華泰茶荘にとって、それは二百年前の台湾、石碇の地でした。林家の先祖が故郷である福建省安渓を離れ、新天地に茶の木を植えたその決意こそが、今日の私たちの礎となっています。この歴史的な一歩がなければ、華泰茶荘の物語は始まりませんでした。
物語の源流は、二百年前に遡ります。
私たちの先祖は、茶の名産地として知られる福建省安渓から海を渡り、台湾の石碇地区に定住しました。そして、故郷の知識と技術を活かしてこの地に茶の栽培を始めたのです。その伝統は今なお途絶えることなく、林家の子孫は現在に至るまで石碇の地に茶園を所有し続けています。
語り手である私は、この血脈を受け継ぐ第五代目として、先祖から続く製茶の技術と、お茶に込められた精神を次世代へと繋ぐ重責を担っています。それは、単に家業を継ぐことではなく、二百年の歴史そのものを未来へと伝承していく使命なのです。
石碇の山々で育まれた茶葉は、やがて台北の活気ある街、大稲埕で新たな歴史を刻むことになります。
確立:百年老店「林華泰茶行」の誕生と大稲埕の記憶
茶業の拠点が台北へと移ったとき、林家は新たな挑戦に乗り出します。それが、卸売業としての「林華泰茶行」の設立です。この一手は、単なる事業拡大ではありませんでした。茶農家が丹精込めて育てた茶葉を、最も純粋な形で消費者の元へ届けるという理念の表明であり、ブランドの信頼を築くための戦略的な一歩でした。この揺るぎない理念こそが、台北の茶文化における「林華泰」の名を不朽のものとしたのです。
祖父・林大村と父・林秀峯が「林華泰茶行」を創業した際の理念は、極めて明快なものでした。それは、「茶農家が育てた茶を、消費者と最短で結びつけること」。中間業者を介さず、品質の高い茶葉を適正な価格で提供するという実直な姿勢を貫き、主に茶葉の卸売販売を手掛けることで、「林華泰茶行」は台北で最も古い茶行の一つとしての地位を確立しました。その信頼の根底には、創業以来ずっと大切にしてきた「茶葉の品質と顧客サービスを重視する」という、決して揺らぐことのない信念がありました。
その名は、やがて街の記憶そのものとなっていきます。「老台北人(昔からの台北っ子)なら、誰もが『林華泰』のお茶を飲んだことがある」「台北で育った者なら、幼い頃に大人に連れられて『林華泰』へお茶を買いに行った記憶がある」と語られるほどに。お客様は、ただ良いお茶を買いに来るのではありませんでした。家族との温かい時間や、街の喧騒といった、自らの人生の一部である「記憶」をも、ここで買い求めていたのです。
しかし、時代の潮流は変化します。伝統的な卸売の形に加え、新たな価値を提供する挑戦が、ここから始まろうとしていました。
革新:精緻なる「華泰茶荘」の黎明
伝統ある「林華泰茶行」の歴史に、新たな一ページが加わります。それが「華泰茶荘」の誕生です。これは、従来の卸売業からの大きな転換点でした。
社会が豊かになり、消費者の価値観が多様化する中で、よりパーソナルで、洗練された形で台湾茶の魅力を届けたい。その想いから、精緻な小包装市場への進出という戦略的な決断が下されたのです。
「林華泰茶行」が茶葉の卸売を主とするのに対し、「華泰茶荘」は贈答用や個人消費といった「精緻な小包装市場」に特化して設立されました。これは、変わりゆくライフスタイルに応え、お客様一人ひとりの嗜好に寄り添うための革新でした。たとえ形態が変わろうとも、その核となる姿勢は不変です。
「林華泰茶行」が築き上げた、茶葉の品質とお客様への丁寧なサービスを最重要視する精神。その伝統を確かに継承することこそが、華泰茶荘の信頼の源泉であり続けています。
この革新の精神は、やがて台湾の国境を越え、新たな挑戦の舞台へと向かうことになります。物語の舞台は、日本へ。
挑戦:日本への留学と、異国での試練
1982年、第五代当主である私は日本へ留学しました。この挑戦は、単なる事業拡大を目的としたものではありませんでした。それは、父や祖父が築き上げた偉大な家業を継ぐ前に、何者でもない自分自身の力を異国の地で試したいという若き日の渇望であり、同時に、台湾茶文化が持つ真の価値を世界に問い直す旅の始まりでもありました。
留学中、父と祖父からは家業を継ぎ、さらに大きく発展させてほしいという期待を寄せられていました。しかし、若さゆえの反骨心か、すぐには台湾へ戻り、その大きな看板を背負う気にはなれませんでした。「異国で自分の実力を試したい」。その一心で、私は東京に「日本華泰茶荘」を設立することを決意したのです。しかし、当時の日本市場は想像以上に厳しいものでした。台湾烏龍茶に対する大きな誤解が、厚い壁として立ちはだかっていたのです。
当時の日本人の多くは、烏龍茶といえば「黒い茶湯」というイメージしか持っておらず、正しい淹れ方を知る人はほとんどいませんでした。本来、台湾の烏龍茶は製法によって多様な茶の香りや果実の香りを持ちます。聞香杯でその繊細な香りを楽しみ、茶湯は黒ではなく、目にも鮮やかな「黄金色で明るい」ものなのです。なぜこのような誤解が生まれてしまったのか。おそらくその原因は、お茶を十分に理解していない貿易商が、本来の品質ではない茶葉を仕入れ、正しい淹れ方や飲み方といった文化的な背景を伝えずに販売してしまったことにあるのでしょう。
この困難な状況を前に、私の心には強い使命感が芽生えました。この誤解を解き、台湾茶のありのままの姿を日本の人々に伝えなければならない。その決意が、次なる大きな飛躍へと繋がっていきます。
伝承と開花:東京・渋谷での文化発信
日本での挑戦は、単に質の良い茶葉を販売するだけでは終われませんでした。それは、台湾茶の背後にある豊かな文化そのものを広めるという、壮大なミッションへと昇華していきました。流行の発信地である東京・渋谷に拠点を構えたことは、この文化を日本の土壌に深く根付かせるための、極めて戦略的な一手だったのです。
開店にあたり、私は「台湾茶の真の特色、そのありのままの姿を、日本の顧客に伝えたい」という強い理念を掲げました。幸運にもその後、東京の繁華街・渋谷にビル一棟を構える機会を得て、この理念を大きく広めるための拠点を築き、事業も良い成績を維持することができました。
私たちの目的は、単にお茶を売ることではありません。「台湾の茶藝文化を広め、より多くの日本人に台湾茶を知ってもらうこと」こそが、開店当初からの変わらぬ理念です。その想いを実現するため、製茶から淹れ方、茶席の設え方までを網羅した一連の専門講座を設計しました。この試みは多くの人々の心を動かし、数々の奇跡を生んだと、今も嬉しく思っています。現在も、東京・渋谷の店舗の一階を茶教室として維持し、台湾茶文化の普及活動を地道に続けています。
日本での経験は、私自身の人生観にも深い影響を与えました。
それは予期せぬ形で与えられた、かけがえのない使命でした。
終章:未来へ続く、茶の道
華泰茶荘の歩みは、二百年にわたる伝統を守りながらも、常に時代の変化に応じて革新を続けてきた道のりでした。石碇の茶畑から始まり、大稲埕の喧騒、そして東京・渋谷での文化交流へ。そのすべてが、一杯のお茶に込められた私たちの想いです。
振り返ってみれば、お茶を通じて多くの人々と出会い、台湾茶文化を紹介できたことは、当初は予期していなかった使命でした。しかし、この活動を通じて台湾茶文化が日本に深く根付いたことは、私の人生における大きな誇りです。「人生は、おそらく直線ではないのでしょう。曲がりくねった道の先にたどり着いて初めて、それが正しかったかどうかが分かるのかもしれません」。私たちの旅は、まだ終わることはありません。
過去から現在、そして未来へ。この曲がりくねった茶の道がどこへ続くのかは誰にも分かりませんが、私たちはこれからも、一杯のお茶に誠実な想いを込めて、この道を歩み続けていきます。
NPO法人中国茶文化協会 (元日本中国茶インストラクター協会) 理事長
林 聖泰 LIN SHENGTAI (2025.10 インタービュー取材)