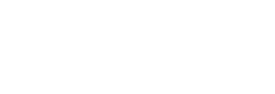唐代の盧仝(ろどう)は、七椀の茶を飲み干し、風を生じて仙人の境地に至ると詠いました。しかし、美食を極めた清代の袁枚(えんばい)は、その「量」に頼る飲み方に一石を投じます。
彼が説いたのは、一滴に凝縮された質と、その後に訪れる悠久の余韻こそが真髄であるという、まさに「烏龍工夫茶」の美学でした。
原詩抜粋
一杯啜盡一杯添,笑殺飲人如飲鳥。
(一杯飲んではまた一杯。鳥が水を叩くようにガブガブと飲む人々を、私は笑わずにはいられない。)
<中略>
我震其名愈加意,細咽欲尋味外味。
(私は名茶の響きに敬意を払い、静かに喉へ送り、その奥底に潜む「味わいの彼方(味外味)」を探り当てるのだ。)
杯中已竭香未消,舌上徐嘗甘果至。
(杯が空になっても香りは留まり、舌の上には果実のような甘みがゆっくりと戻ってくる。)
嘆息人間至味存,但教鹵莽便失真。
(ああ、この世の至高の味よ。ガサツに扱えば、その真髄は指の間からこぼれ落ちてしまう。)
盧仝七碗籠頭喫,不是茶中解事人。っっっっっz(あの盧仝の「七椀」のガブ飲みも、本当の意味で茶を解する者の振る舞いとは言えないな。)
味外味と回甘
袁枚が探求したのは、喉を過ぎた後に訪れる風景、すなわち「味外味(みがいみ)」です。
一瞬の刺激としての味ではなく、飲み込んだ後に喉からふわりと戻る甘み(回甘)や、空の茶杯にいつまでも漂う芳醇な残り香(杯底香)。
この目に見えない響きこそが、お茶の真価値だと彼は喝破したのです。
ときには盧仝のように心身を解放して豪快に飲み、ときには袁枚のように感覚のひだを広げ、深い余韻を辿る。そのどちらの楽しみも、お茶という宇宙が持つ素晴らしい魅力です。
明日の茶席では、ぜひ袁枚になったつもりで、最後の一滴のあとに訪れる「景色」を探してみてください。その一杯が、皆様の心に豊かな安らぎを広げてくれるはずです。
(写真・文章 NPO中国茶文化協会 理事長/林華泰茶行・日本華泰茶荘 五代目店主 林聖泰)